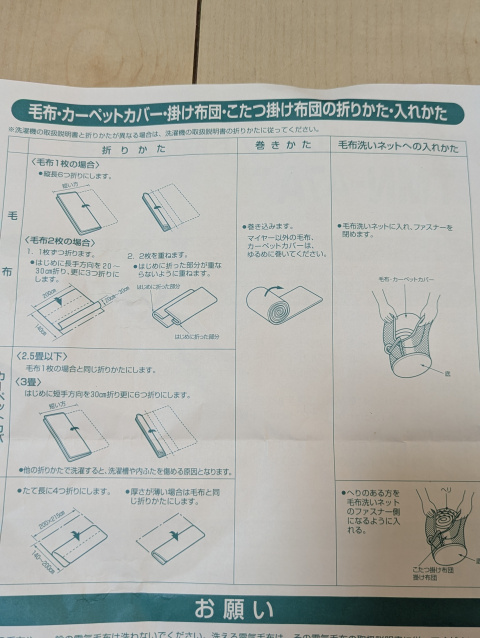ホームセンターで掃除に役立ちそうな道具を見つけたので試しに買ってみました。

ペットボトルに取り付けることで手動の洗浄機になるというノズルです。柄の部分にプランジャーが内蔵されており、それを前後させることでペットボトル内の圧力が高くなっていきます。ある程度圧力が高くなったらトリガーを引くと高圧の空気に押し出されて水がノズルから出てくるという仕組みです。
仕組みとしては昔ツクダオリジナルから発売されていた”エアーウォーターガン”に似ています。
実用性
暑いうちにサッシの掃除をしようと思っていたのでアルミサッシの掃除に使ってみました。ノズルは回すことで霧吹きか水流を選べます。霧吹きにした場合は水圧はあまり感じられません。
水流にした場合は高圧洗浄機のようにはいきませんが、ある程度勢いのある水が出せます。狭いところにも届くので、サッシにたまった土埃を飛ばすくらいであれば十分でした。こびりついた汚れを圧力で落とすようなことはさすがにできないように思います。
注意点
人力とは言えペットボトル内の空気に圧力をかけて水を噴射する道具なのでいくつか注意点があります。
ペットボトル内に空気がないと噴射できない
これは考えてみれば道理なのですが、ペットボトル内の空気部分の圧力を高くして水を押し出すという仕組みになっています。そのため、ペットボトル内を水で満たしてしまうと噴射ができなくなります。
全体の2/3位まで水を入れると効率よく使えます。
ノズルをペットボトルにしっかりねじ込んでおく必要がある
このノズルはペットボトルのキャップの要領でボトルの口にねじ込んで使いますが、この固定が甘いと圧力が高くなってきた時に急にボトルが飛んで行くことがあります。おそらくですがペットボトルの種類との相性もあると思います。
いくつか試しましたが、サントリーのCCレモンのものが良さそうでした。
ボトルを外す時に減圧しておく必要がある
これも同様ですが、作業終了後にボトルを外す場合、事前にトリガーを引ききってペットボトル内部の圧力を抜いておかないと、ノズルを緩めた時に水が噴き出す恐れがあります。圧力のかかった状態でボトルをはずそうとしないよう注意が必要です。
本体価格が1,000円しませんし、100%人力のアイテムであることを前提とすれば十分な性能なのではないかと思います。霧吹きモードも植物の世話や窓や網戸の掃除に使えたのでお試し購入だったものの意外に重宝しています。