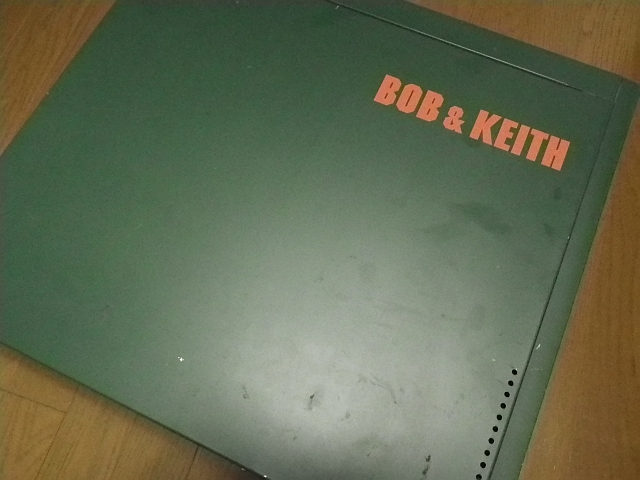RT-AC68Uを買ってから1か月くらい経ちます。
とりあえず無線機器は高速で接続でできるので満足していますが、せっかく色々できそうなので取り扱い説明書や管理用コンソールを眺めてみました。
・管理用コンソールで接続中の機器をチェックできる
パスワードを設定しているのでもちろん誰でも接続できるわけではないのですが、接続機器を一覧表示できるので心理的に安心感があります。
・ルータの設定に問題がないか自動チェックするモードがある
ネットワークには正直疎いのですが、ルータの設定をチェックし「○○はオフにした方がよりセキュアですよ」といった形で設定をお勧めしてくれます。
各項目について調べると勉強にもなって一石二鳥です。
・USB-HDDをつなぐとネットワークストレージ化できる
外出先から家のHDDの中身を見たいという需要は今のところないものの、便利な機能です。
単純にPCにUSB-HDDとして接続するよりはNAS状態にした方が何かと使い出があるかもしれません。
というわけでなかなか基本性能以外にも色々気が利いています。