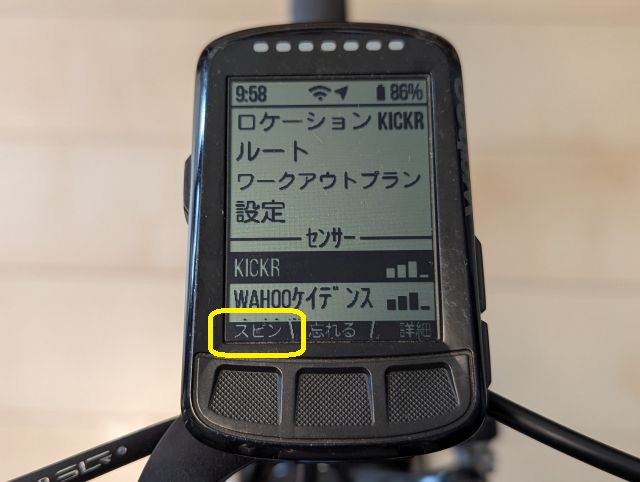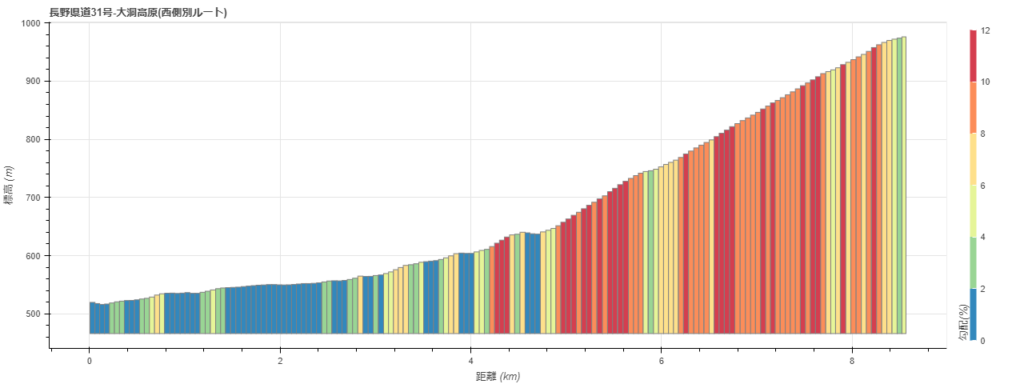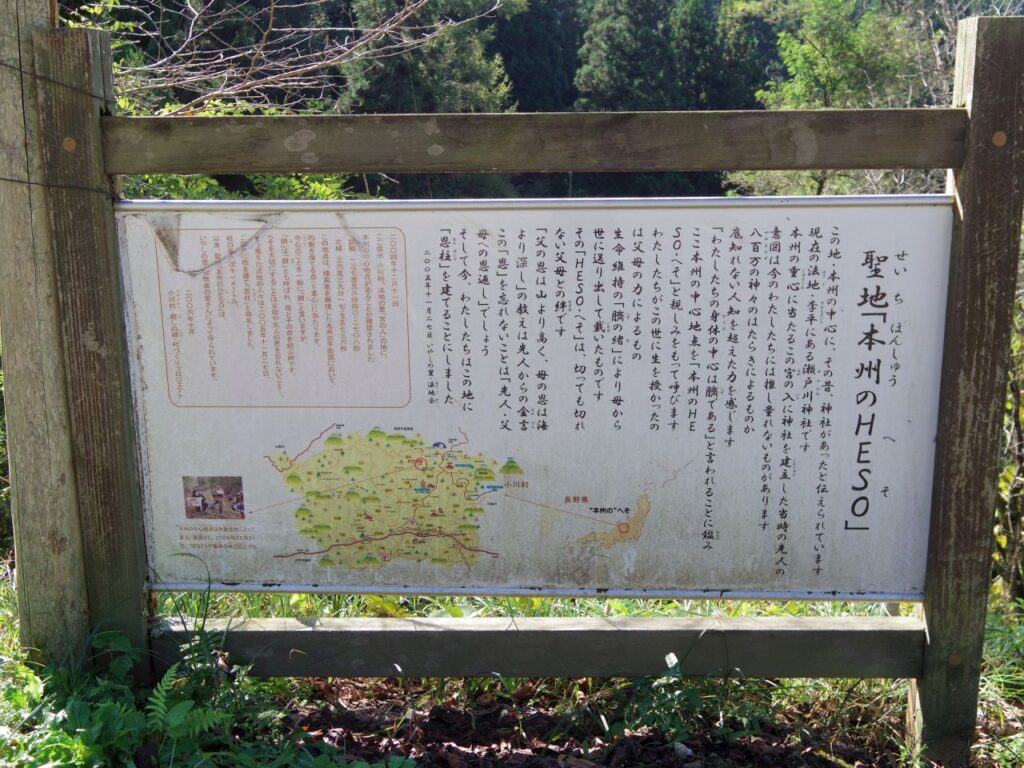ブラウザのお気に入り整理をしているときに時々買い物をしていたイギリスのwiggleという自転車用品の通販サイトにアクセスしたところ、全く関係ないと思われる情報サイトに中身が置き換わっていました。
wiggleにはしばらくアクセスしていなかったので何があったか調べてみたところ、wiggleは2023年の夏には経営難になっており、親会社のSigna Sports Unitedから資金投入が予定されていたところそれが引き揚げられ、整理が必要な状態になってしまったようです。
Wiggle CRC put up for sale as administrators step in
[cyclingnews.com]
その後イギリスのFrasers Groupが買収し、Webサイトについても再オープンという形になって今に至っているようです。
Frasers Group reportedly set to scoop up remnants of WiggleCRC for less than £10 million
[cyclingnews.com]
以前あったwiggleの日本語版サイトは整理時にドメインが放棄され、誰かが放棄されたドメインを使っているのではないかと思います。
2010年代は相対的に日本円が高かったので、このwiggleを始め海外の自転車用品サイトで買い物をするのが流行った時期がありました。私もその頃にwiggleを知りました。
その後日本円が安くなってしまったので、「海外通販でお得に買い物」という感じではなくなってしまったのですが、私はwiggleで取り扱いのあるdhbのアパレルがとても気に入っていたので、その後も時々利用していました。
現在営業しているwiggleのグローバルサイトを見る限り、商品欄に”海外発送可”となっているものは海外発送対応しているそうです。また、日本への送料も15.83スターリングポンド(約3,000円)からと明示されているので、買い物をすること自体は可能なようです。
上記のニュースには新型コロナウイルスの影響による需要の乱高下や物価高が原因と書いてありましたが、まさかこんなことになっているとは思いませんでした。