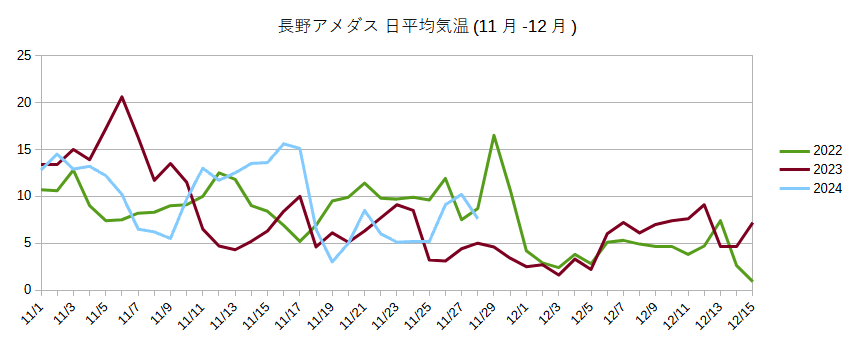2023年の10月に実証実験として実施されていた長野電鉄のサイクルトレインを利用しました。2024年になり、サイクルトレインが正式に運用開始となったため利用してみました。
予約の仕組み
実証実験時と大きく異なるのは予約の方法です。実証実験時には専用のアプリから予約をする方式でしたが、2024年度版では長野電鉄のWebサイトから予約する方式になっています。長野電鉄の特急列車などを予約する方法と同様です。
Webサイトのアカウントも共通なので、既に長野電鉄Webサイトのアカウントを持っている方であれば簡単に予約ができます。もちろんアカウントなしでも予約可能です。支払いはクレジットカードで行います。
予約が完了するとPDF形式の乗車証がダウンロードできるので、これをスマートフォン等で表示するか、または紙に印刷して提示すると乗車できるという仕組みになっています。
注意が必要なのは予約の受付期間です。実証実験時には当日発車寸前まで予約が可能でしたが、2024年度版の予約は前日24時までとなっています。当日での予約も一応可能ですが、その場合は長野電鉄の問い合わせ窓口に電話して予約することになります。
実際の乗車
今回は長野駅から信州中野駅まで乗車してみることにしました。長野電鉄の長野駅は地下にありますが、地上からエレベーターやスロープつきの階段で駅にアクセスできるのでこの点は心配要りません。
 早朝の長野駅です。
早朝の長野駅です。
長野駅での改札ではスマートフォンで乗車証を提示しました。帰りの切符は予約済みかを確認されましたが、帰りは自走するので大丈夫と伝えました。長野駅の場合改札からプラットホームまでも1階分くらいの高低差がありますが、エレベーターがあるのでこれを使います。エレベーターでは対角線上に車体を置き、ハンドルを大きめに切ればそのまま乗せられます。

長野電鉄8500系のT2編成でした。サイクルトレインの場合は先頭車両または2両目の車椅子用スペースを利用することになるので、先頭車両に乗りました。
信州中野方面の始発列車(6:15発)だったのであまり人は乗っていませんでした。ロングシートに座らせてもらい、乗車中は自転車を進行方向に向けて手で支えるという方法で約45分乗車しました。45分乗っていると結構自転車を支えるのが重労働に感じました。

というわけで無事に信州中野駅に到着しました。信州中野駅でも改札で乗車証を提示しました。駅係員の方は「へえ~こんな感じなんですね~、信州中野で降りられる方があまりいないみたいで…(笑)」と仰っていました。サイクルトレインを利用される方は湯田中まで乗車する場合が多いのかもしれません。
その後親切にエレベーターの場所などもご案内いただき、和やかな感じで降車時の改札を終えて出発となりました。
利用してみて
実証実験時と予約のシステムが変わっていますが、特急列車等も含めて一貫したシステムでの取り扱いになっているので分かりやすくなっていると思います。予約や決済に至るまでのユーザー体験も便利でなかなか良かったと思います。
輪行袋を使う輪行に対して、サイクルトレインは何と言っても荷物が少なくて済むのがとても楽です。通常の輪行の場合、装備にもよりますが輪行袋とスプロケットカバー、エンド金具等で1リットル弱ほどの収納容積が必要です。そうなってくるとサドルバッグも大きい物にならざるを得ず、必然的に荷物がどんどん増えていきます。
一方でサイクルトレインの場合は通常のサイクリング時と同様か、万全を期す場合でもクリートカバーがあればまず問題ないというところなのでほとんど荷物は増えません。これは非常に大きいアドバンテージなのではないかと思います。
前日までの予約となったので帰路の利用は少々難しくなった感はありますが、行きに使う分には非常に便利だと思いました。またお世話になることもあろうかと思います。