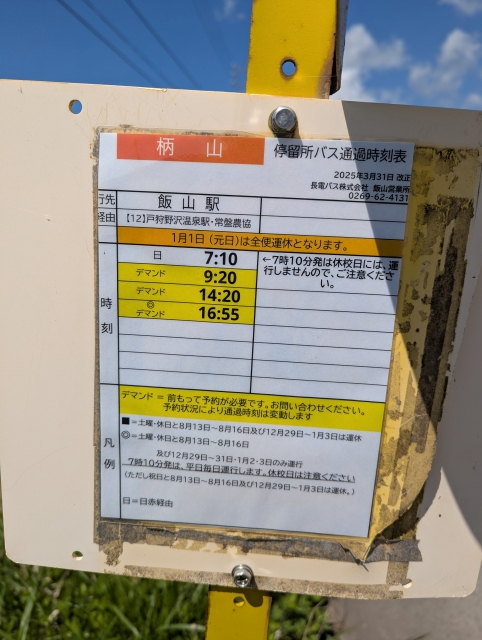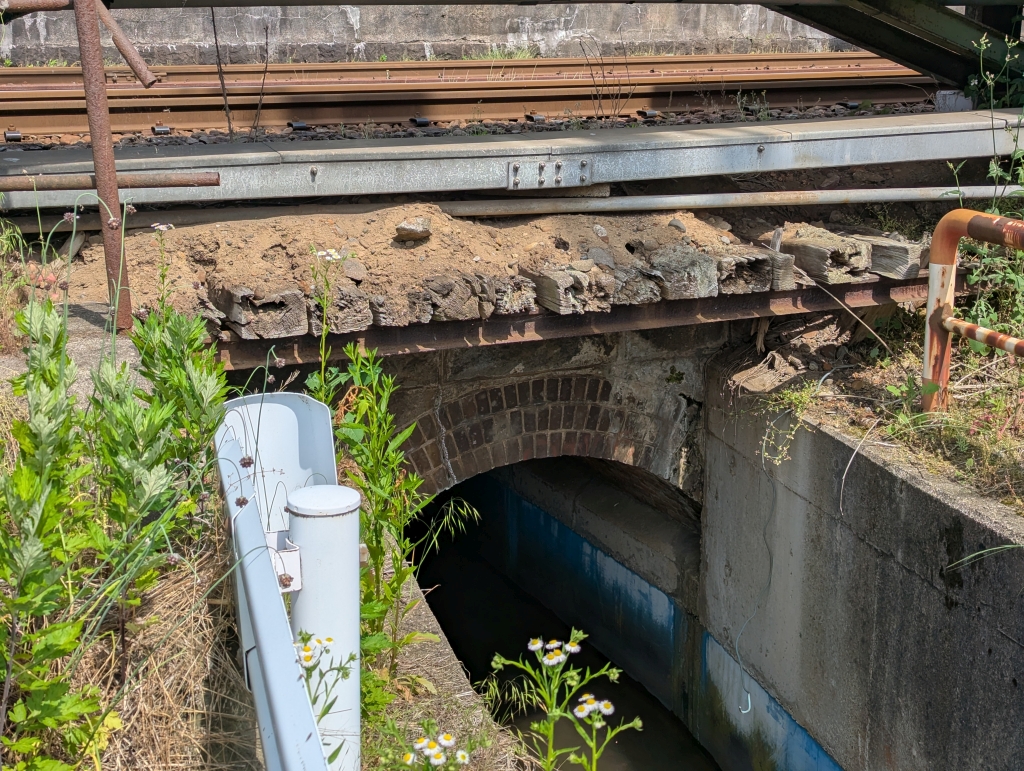えちごトキめき鉄道としなの鉄道のサイクルトレイン制度
旧信越本線が転換されたえちごトキめき鉄道としなの鉄道にもサイクルトレイン制度があります。サイクルトレイン制度にも様々なものがありますが、えちごトキめき鉄道としなの鉄道のものは利用区間と利用できる列車が限定されているというものです。
【北しなの線】サイクルトレインのご案内
[しなの鉄道Webサイト]
【5/1再掲】サイクルトレインの実施について
[えちごトキめき鉄道Webサイト]
双方の路線で上り下りとも10時台から16時台の列車が利用できます。えちごトキめき鉄道としなの鉄道の北しなの線は妙高高原駅で連絡できるため、サイクルトレインを続けて利用することも可能です。今回はえちごトキめき鉄道の新井駅から北しなの線の豊野駅までを通しで利用してみました。
上越方面は長野市周辺からだとまあまあ距離があって今まであまり探検できていないので、帰路をサイクルトレインにすることで上越エリアでの行動距離を増やそうというもくろみです。
上越方面から長野方面に移動する場合の乗車プラン
サイクルトレインは日中しか利用できないので往路についてはいつものように早朝に出発して妙高高原を越えます。昼過ぎから夕方にかけてのサイクルトレイン対応列車のどれかで豊野駅まで移動し、そこからは自走して帰路につくという流れです。
このプランだと対応する列車の組み合わせは以下の通りになります。
| 新井駅発 | 妙高高原駅着 | 接続時間 | 妙高高原駅発 | 豊野駅着 | 全体移動時間 |
| 12:15 | 12:43 | 0:23 | 13:06 | 13:34 | 1:19 |
| 13:25 | 13:51 | 0:47 | 14:38 | 15:08 | 1:43 |
| 15:00 | 15:27 | 0:27 | 15:54 | 16:23 | 1:23 |
| 16:09 | 16:34 | 0:08 | 16:42 | 17:10 | 1:01 |
えちごトキめき鉄道と北しなの線は妙高高原駅で接続するようなダイヤ編成になっているのですが、こうしてみると組み合わせによって結構差があることが分かります。
サイクリングを終了するタイミング的には新井発13:25のものが良さそうではあったのですが、さすがに接続時間47分はちょっと長すぎてもったいない感じがしたので、今回は上越エリアでのんびり目に時間を使って15:00発の列車で帰ることにしました。
新井駅
 鉄筋平屋の横に長い感じが国鉄時代からの歴史を感じさせます。
鉄筋平屋の横に長い感じが国鉄時代からの歴史を感じさせます。
今回利用開始駅は新井駅に設定しました。サイクルトレインの利用区間としては1つ直江津方寄りの北新井という駅からになっていますが、北新井駅は無人駅なのでいきなりサイクルトレインで乗車していいものかどうかが不安になります。新井駅であれば有人駅で、ルールの確認等もできて良さそうなので新井駅を拠点にしました。
えちごトキめき鉄道でサイクルトレインを利用する場合は乗車券の他に手回り品きっぷ(290円)が必要です。自動券売機では買えなかったので、窓口で「サイクルトレインを利用したいので手回り品きっぷをお願いします」と申し出たところ速やかに手回り品きっぷを発行してもらえました。乗る区間と決まっていれば乗る列車についても申告する必要があります。
新井駅では妙高高原方面の列車に乗る際に跨線橋を通ってホームを移動する必要がありますが、エレベーターなどはないので自転車を担いで階段を上り下りすることになります。スポーツバイクなら多少は軽量なのでなんとかなりますが、一般車だと大変そうな気がします。
妙高高原駅
妙高高原駅で列車を乗り換えます。対面乗り換えできるので楽で良かったです。

 しなの鉄道に乗り換えます。SR1系は最新型ゆえか揺れが小さくて利用しやすかったです。
しなの鉄道に乗り換えます。SR1系は最新型ゆえか揺れが小さくて利用しやすかったです。
豊野駅

サイクルトレインが利用できる終点である豊野駅で下車しました。豊野駅は駅コンコースまでエレベーターがあるので自転車の運搬がしやすいと思います。
改札を出る時に駅係員の方に呼び止められたので何かルールを勘違いしていたのかと思ってドキッとしましたが、お話を聞いてみると「よろしければサイクルトレインのアンケートに回答してほしい」ということでしたので回答しました。しなの鉄道はちゃんとサイクルトレインの効果測定をしているのが真面目だと思いました。
利用してみて
長野駅から上越方面に向かうと、高田城趾まで片道70km、直江津港までは片道80km近くになります。これだと単に最短距離を往復するだけで結構な大仕事になってしまいます。
しかし新井駅から豊野駅までサイクルトレインを利用すると距離にして48km・獲得標高で約790mをカットすることができます。ざっくりな計算ですが現地で48km分余計に走れることになるので行動範囲が広がります。
料金は手回り品きっぷの分を含めても新井-豊野間で1,450円なのでアップチャージに対して得られるメリットは大きいように思います。上越妙高から長野まで北陸新幹線利用で輪行すると2,860円かかるので大分割安です。その代わり北陸新幹線ルートは21分で長野に着くので、こちらはこちらでメリットのあるプランだとは思います。
一方、そもそもの列車本数が少ない区間なので乗車駅への到着時間を調整するのが難しく感じました。この点は現地の土地勘がまだあまりないからという部分もあると思います。トキ鉄に関しては旧北陸本線の日本海ひすいライン区間についてもサイクルトレインの設定があるので、そちらもチャンスがあれば検証してみたいと思います。