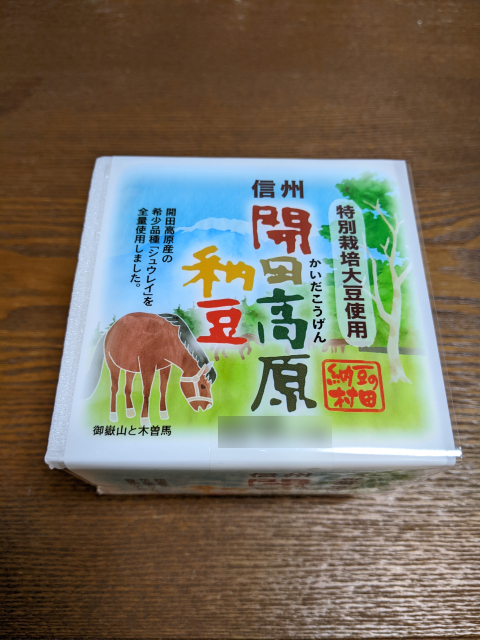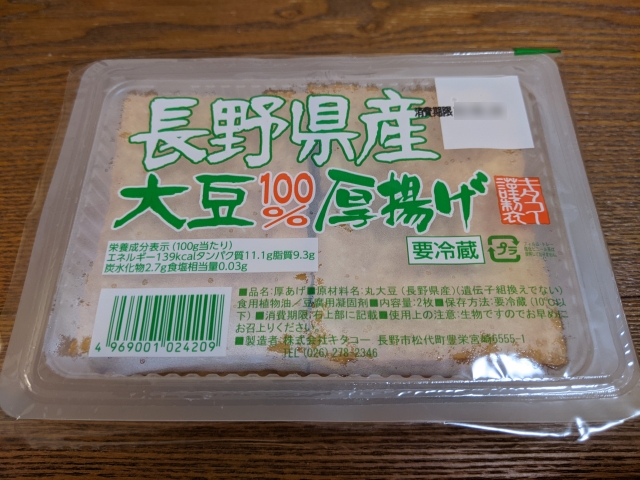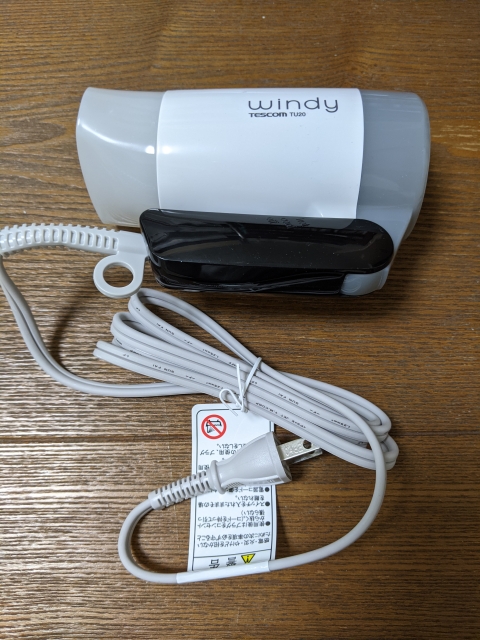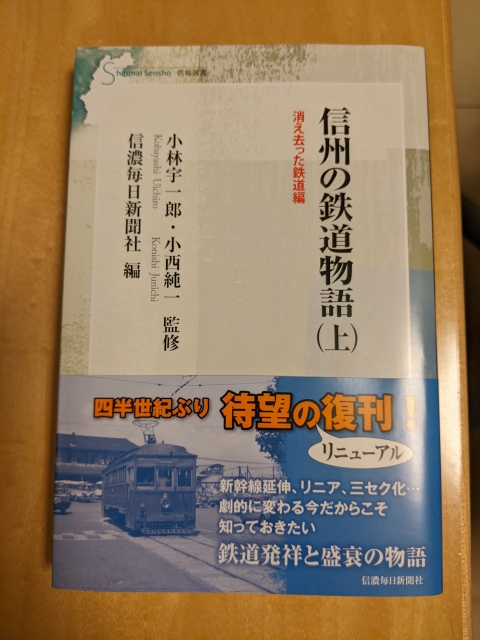2019年の台風19号の被害で長らく通行止めだった東御市の海野宿橋がとうとう2022/3/1に開通するとのことです。
東御市道 白鳥神社線が3月1日に復旧完了。海野宿への主要アクセス道路が再開通。2019年台風19号で「海野宿橋」流出など被害
[トラベル Watch]
2021年度中の復旧を見込むということだったので、予定通りに復旧が完了することになります。
この橋が通行可能になると国道18号の海野宿入口交差点から直接海野宿方面に入ることができ、観光に非常に便利です。また海野宿入口交差点からはしなの鉄道の大屋駅まで右左折なしで移動できる海野バイパスと呼ばれる道路があり、こちらも良く通らせてもらっています。
ぜひ動画などで紹介したい道路なので、復旧後に自転車で走ってみるのが楽しみです。