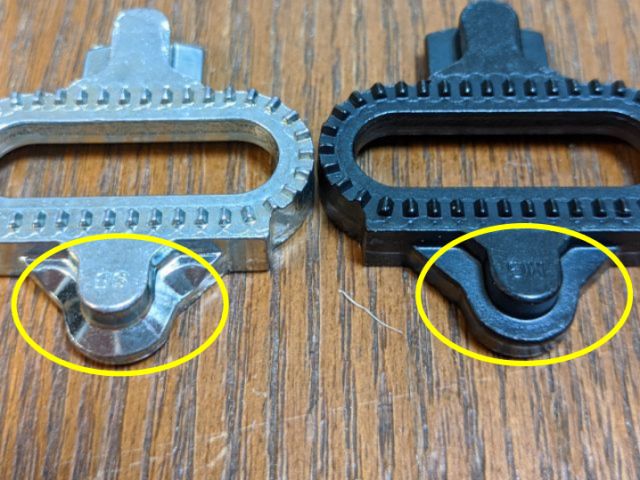タルタルーガ用に替えのチューブを買いました。

タルタルーガ Type Sportのタイヤ径はインチで表すと”20インチ”になるのですが、20インチの場合チューブやタイヤを買うときには注意が必要になります。
タルタルーガ Type Sportには各グレードともAlexrimsのDA22リムを使ったホイールが装着されています。DA22にはいくつかバリエーションがありますが、タイヤ内径451mmのものが採用されています。このタイヤ内径が重要なポイントです。
自転車のタイヤやチューブのサイズにはフレンチ表記、インチ表記、そしてETRTOという共通規格の3種類の表記法があるのですが、このうちインチ表記でタルタルーガ Type Sportのタイヤを表現すると20 x1-1/8という表記になります。ETRTO表記の場合は28-451という表記になります。
しかし困ったことに、インチ表記で同じ20 x 1-1/8なのにも関わらず、ETRTO表記が28-406というサイズが存在します。同じ”20インチ”なのですが、インチ表記だけを当てにして買うと直径が5cmくらい違うチューブを買ってしまうことがあり得る、ということになります。
店頭でパッケージを確認して買えれば良いですが、通販で買う場合は慎重に確認した方が良さそうです。ETRTO表記をしてくれている通販サイトで買うと間違いないと思います。