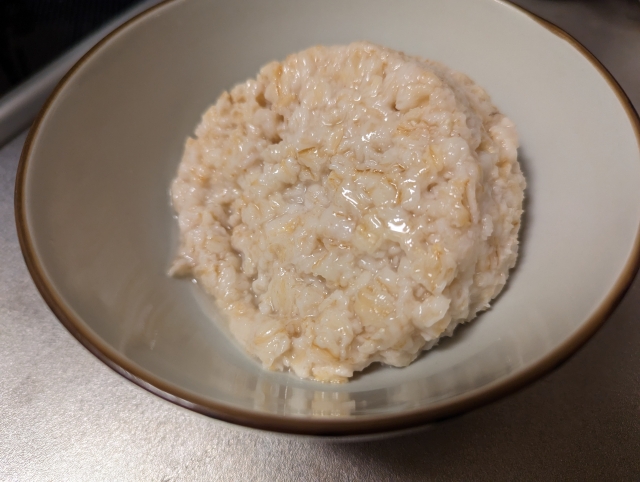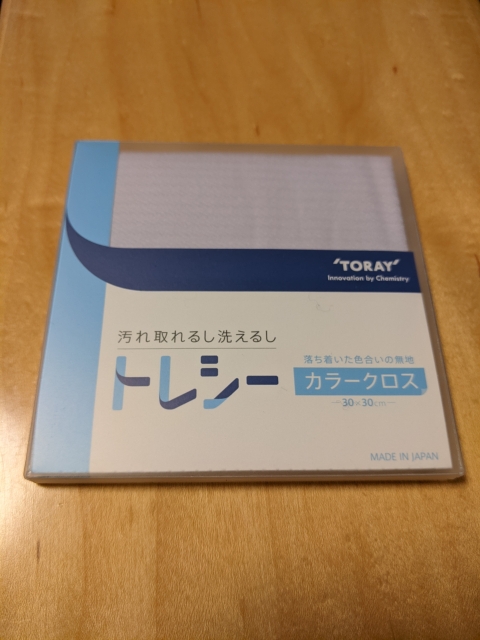暖房していても室内はそれなりに冷え込んでくるので、屋内でも防寒用品を色々と身につけています。防寒でよく言われるのが「首を冷やさないようにすると良い」という話です。
つまり”首”、”手首”、”足首”を冷えないようにすると良いというわけです。これらの部位はいずれも筋肉や脂肪が薄く、太い血管が皮膚のすぐ下を走っているので、確かに冷やしてしまうと冷えが全身に波及しそうです。
首に関してはネックウォーマーなどで保温していますが、手首・足首の保温をどうしたら良いか悩んでいました。そこで幹線道路沿いに良くある実用衣料のお店を探索したところ、足首ウォーマーが販売されていたので買ってきました。

100%化学繊維でできており、柔らかく着用しやすくなっています。価格は驚きの300円でした。一応足首用として売られていましたが、手首用として使うこともできるのでとても便利です。安かったので色や編み方が違うものを複数買いました。
ちょっとしたアイテムですが、これがあるだけでも結構手先足先の冷えが違ってきます。もっと早く気づいて入手しておけば良かったと思います。