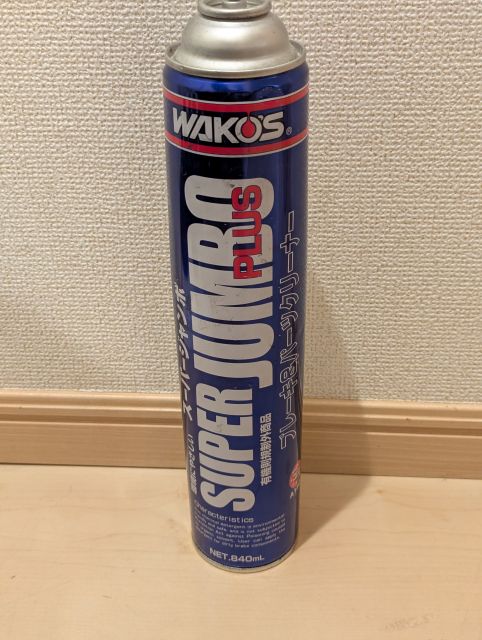長野市街地から鬼無里方面に向かう国道406号の戸隠橋付近に通行できない古そうなトンネルがあり、以前から気になっていました。鬼無里から長野市街地に向けて走ってくるとどうしても目に入るので、2016年に旅行で来て初めて通行した時から気になる存在でした。
 これです。写真は2016年10月に撮影したものですが、今も状態はあまり変わっていません。
これです。写真は2016年10月に撮影したものですが、今も状態はあまり変わっていません。

わかりにくいですが川場隧道(トンネル)と読み取れます。もしかしたら川湯かもしれません。
通行止めになっているので徒歩であったとしても調査は不可能なのですが、各種インターネットで公開されている地理情報類を使って遠隔調査をしてみることにしました。
長野市道路台帳網図
通行止めの看板が長野市名で掲出されていることから市の管理道路(市道)の可能性が高いものと判断をしました。長野市の場合市が管理する道路についてはインターネット上で道路台帳図と道路台帳網図が閲覧可能です。
これによるとこのトンネルは長野市道戸隠南432号線という路線であることがわかりました。また、この道路の先に戸隠南435号線という道路が接続していることもわかりました。
Openstreetmapではなぜかこの432号線が図示されており、線形が大体わかるようになっています。
まず気になったのはこのトンネルを抜けるとどこかに通り抜けできるのかということでしたが、少なくとも道路という形では行き止まりになっているようでした。
こうなってくるとこの道路が何のために作られているのかが気になってくるところです。
国土地理院の空中写真閲覧サービス
そこで今度は国土地理院の空中写真閲覧サービスで上空から何があるかを調べてみることにしました。このデータは過去の写真も含まれているので、現在はなくなった施設などがある場合でも調査が可能です。
いくつかの年代で比較ができるとよかったのですが、場所が山間部ということもあってか1976年と2010年の写真しか使えそうなものがありませんでした。しかも1976年は撮影縮尺が1/15,000なので少々小さめです。
比較してみるとこんな感じになります。
 2010年
2010年
 1976年
1976年
※本エントリ内の写真はいずれも国土地理院の空中写真閲覧サービスのものを加工
かなり大ざっぱではありますがおおよそ同じ場所を切り出してみました。こうしてみると1976年の写真は道路網が2010年と比べてかなり未発達に見えます。一方で田や畑、または人の手の入った山の面積は1976年の方が圧倒的に広く見えます。2010年の写真で見るとかなりの面積が自然に帰っているような印象です。

今回のトンネルの位置をだいたいで写真上に落としてみるとこんな感じになります。道路の先に何があるかというとどうも田んぼだったようです。山間地なのでいわゆる棚田のような形態です。
わかったこととわからないこと
なんとなくこれでこのトンネルが田んぼへのアクセスに使われていた道路らしいことがわかりました。しかしここで少々疑問が出てくるのが、果たして個人の田畑にアクセスする道路のために市がトンネルまで作ってくれるものだろうかということです。
1976年の写真からは読み取れませんでしたが、元々トンネルの先に人家があり、生活用の道路を改善するためにトンネルが作られた、などの経緯が想像できます。
調べてみたら逆に謎が深まってしまいましたが、いろいろと興味深いことがわかり面白い調査でした。