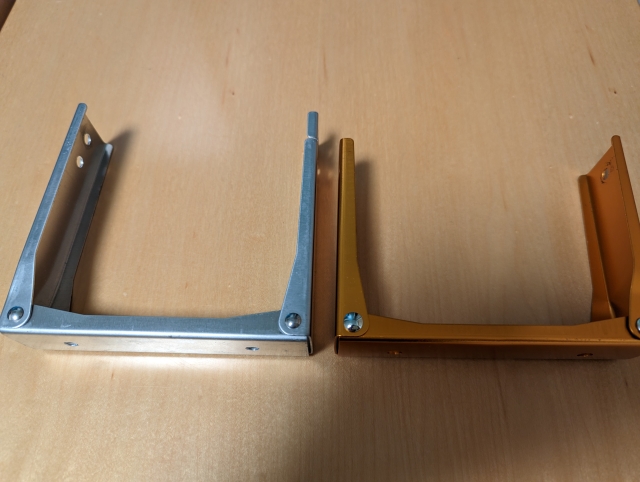一時的に寒さが緩む日があったので、屋外を自転車で走ってみました。自転車については先日全体的な点検と消耗品の交換を済ませてあります。

春先恒例の千曲川サイクリングロードです。2-3日前に雪の日もありましたが、雪は道路脇にわずかに残るのみとなっていました。

遠くを見ると山の斜面、特に日当たりの悪い北側にはまだまだ雪が残っています。現在時点ではサイクリングロードについては問題なく走行ができました。
自転車の方はほとんど新車のようなものなので、メンテナンスとはいっても仕様の変更は行いませんでした。2022シーズン中にヘッドパーツが大分緩んでハンドルがクルンクルン回るようになってしまっていたところ、プロの技で絶妙な加減に調整してもらったのでとても快適になりました。