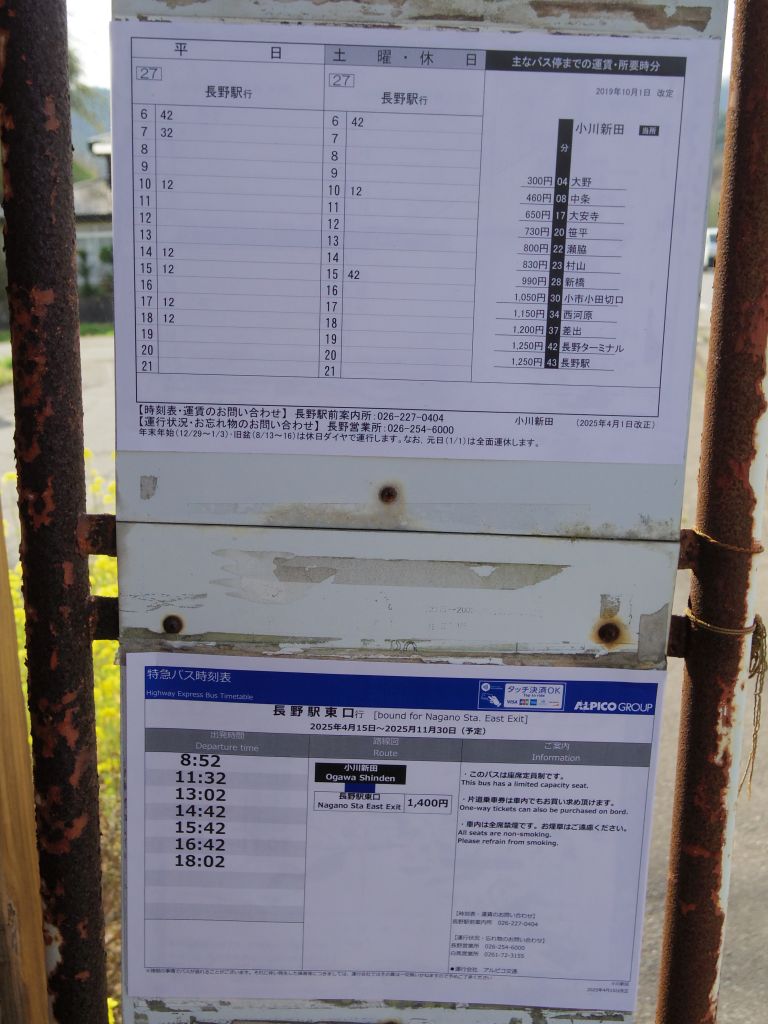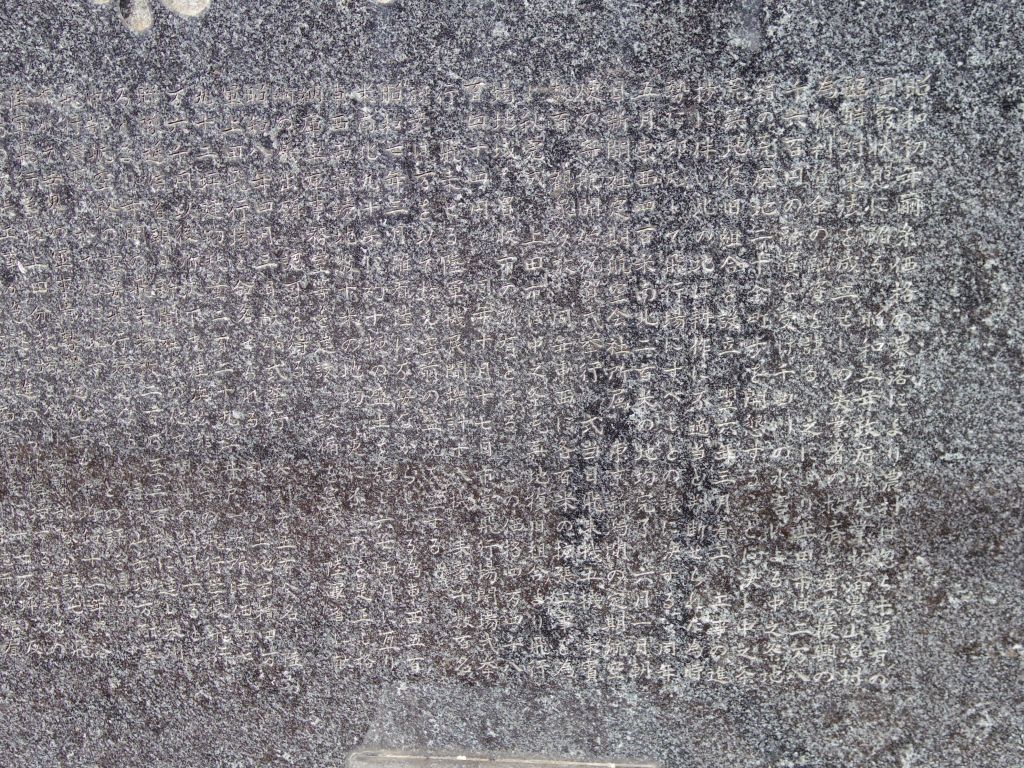鬼無里の町から奥裾花自然園方面に向かう途中に岩下橋という橋があります。この橋の隣に旧橋が解体されずに残っています。

こんな感じで、朽ちるがままに任されているといった感じです。今まで何度も通行しているはずですが、現道よりも一段下に架かっているせいかなんとなく通り過ぎていました。
銘板を確認したくなりますが、橋の周辺が植物に覆われていてこの時期であっても接近は困難です。また、設備の老朽化が原因で不意の事故にあっても困ります。そこで現道の方からスマートフォンのズーム機能を使って銘板の写真を撮りました。

銘板の周辺すら見づらい状況ですが、かろうじて昭和37年・・・という部分が読み取れます。1962年竣工だと築63年ということになります。一般的に橋は40年くらいが耐用年数らしいので、使用されなくなるのもやむなしというところだと思います。
現在の新岩下橋がいつ竣工したかも調べてみたのですが、ちょっと調べた程度では確実な情報を発見することはできませんでした。