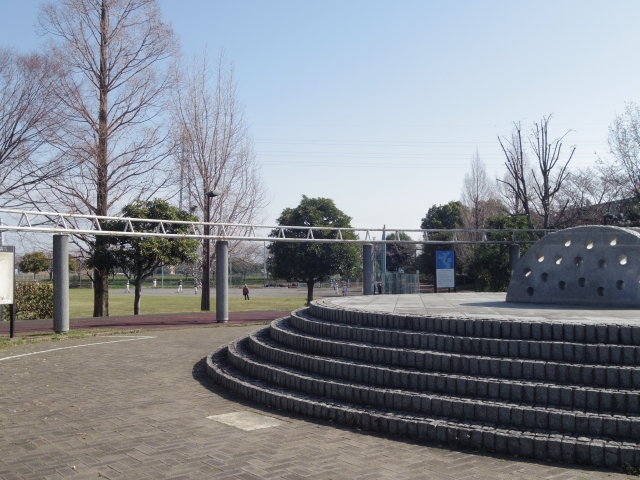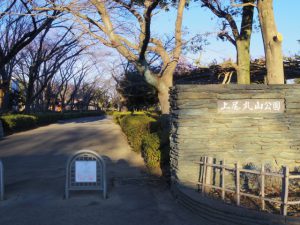2日目はこちらも前から計画していた長野電鉄河東線の廃線跡を走ってみることにしました。
長野電鉄は現在長野線と呼ばれる長野-湯田中間を元東急車や元ロマンスカーなどが走っていますが、かつては屋代線と河東線という路線もあったんだそうです。これらの区間が廃止になったのは比較的最近の話なので、まだ痕跡も明瞭だろうということで興味がありました。
まずはルートインコート千曲更埴からスタートです。日中は暑かったですが朝は長野らしく少々肌寒く感じます。
国道403号で松代-須坂方面に向かいます。実は長野電鉄屋代線の線路は国道403号と並行する箇所が多いのですが、今回は河東線を見たかったので屋代線については次回以降に別途走ってみたいと思います。
千曲川の堤防沿いを走る区間もあります。
千曲川の高水敷です。荒川や利根川に負けない広大さだと思います。