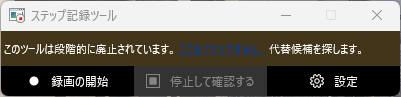発生した事象
表題の件について相談を受けました。特にOutlookやPCの設定は変更していないのにOutlookを起動するときに”プロファイルの読み込み中”と表示されるところから進まずに起動しないという問題です。
最初はよくあるプロファイルの破損かと思い、新しいプロファイルの作成を試しました。メールの送受信テストまではうまくいくのですが、最終的なプロファイルの保存のところでなぜかフリーズして作業が完了しないという問題が発生しました。
当該PCのOSはWindows11の24H2、使っているOutlookはM365 Personalのものです。
PSTファイルの確認
OutlookはPOP3プロトコルを使用し、送受信したファイルはローカルのPSTフォルダに保存していました。そこでPSTファイルの状況を見に行きました。
PSTファイルはOnedrive内のドキュメントフォルダ内にあり、デフォルトの保存先から変わっていないようでした。しかし、妙なことにOutlookが起動していないのに同期中のままステータスが変わりませんでした。
対処
Resmon.exeで当該ファイルを握っているプロセスを調べてみると、Searchprotocolhost.exeが利用していました。そこで、Searchprotocolhost.exeと念のためOnedriveのプロセスを終了し、PSTファイルをOnedriveの同期がかからないフォルダにコピーしました。
その上で、コピーしたPSTファイルを参照するように新たにプロファイルを作成したところ、Outlookが正常に起動することが確認できました。
原因が今一つはっきりしないのですが、状況から見てPSTファイルのOnedrive同期に何らかの問題が発生していた可能性があります。Outlookはデフォルトで ドキュメント\Outlook ファイル フォルダにPSTファイルを保存してしまうので仕方ない側面はあるのですが、このデフォルト設定はどうにかならないものかなと思います。