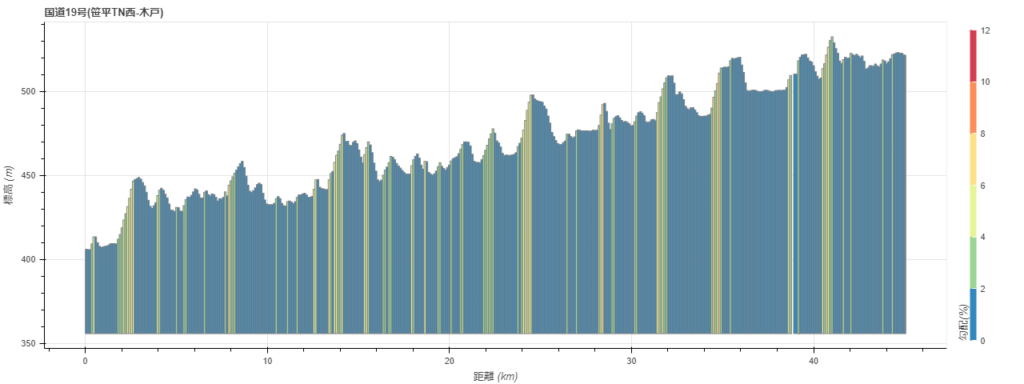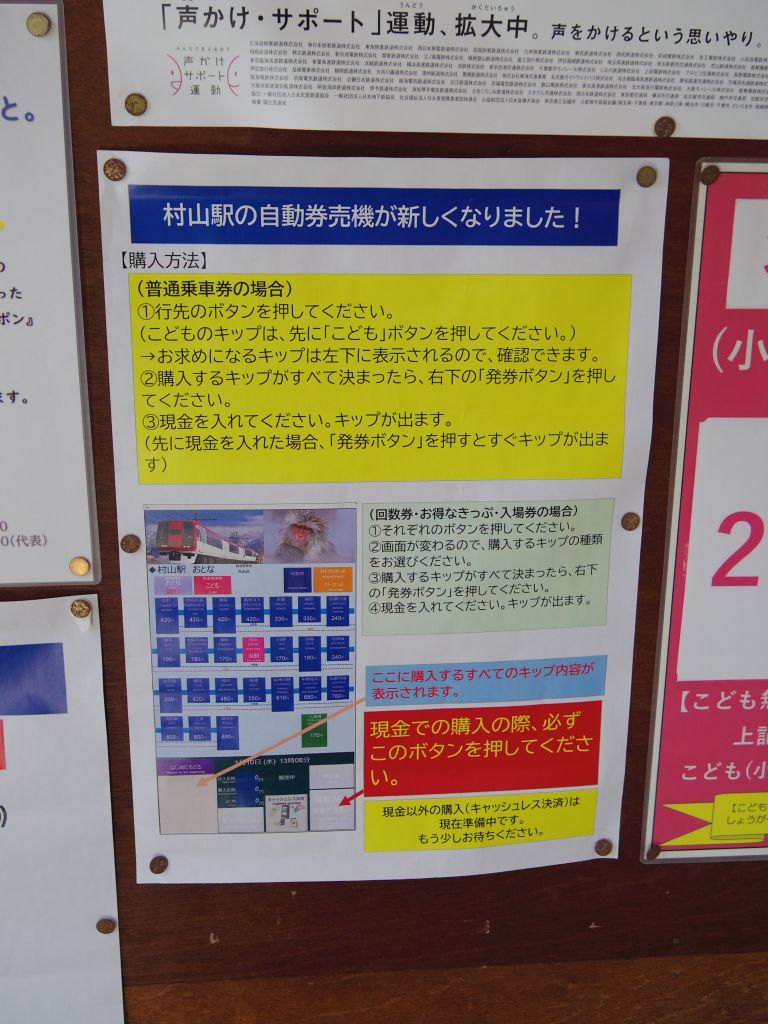3月に交換したIRCのASPITE PROですが、とても快適に使えています。グリップというか地面に対する接地感がしっかりしている印象があり、割と安心して走行できる感じがします。
少々気になっているのは新品の段階から割と異物が刺さりやすいということです。春先は道路上に異物が落ちていることが多いのである程度仕方ないのかもしれませんが、連続して割と大きなガラス片が刺さっていることが多いように感じます。


何かとものが刺さりながらもパンクはしていないので結果としては優秀なのかもしれませんが、今後トレッドが減っていった時のことを考えると心配ではあります。