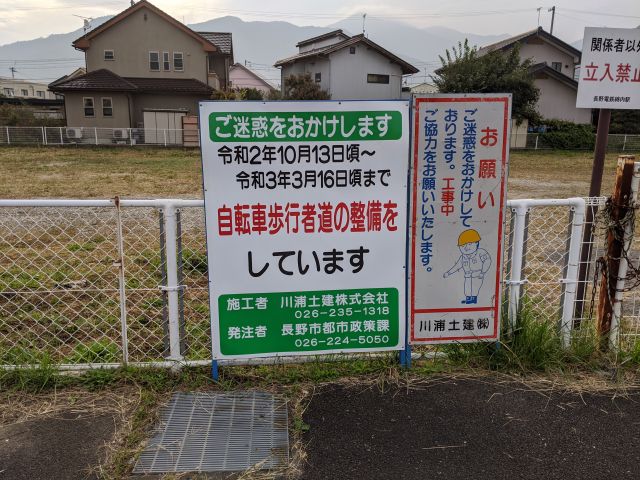須坂市の四阿山方面にある豊丘ダムに行きました。こちらの方面だと県道58号や国道406号がメインルートですが、交通量が多いのであえて裏道っぽい道を通るルートにして見ました。
途中に通る県道349号に蓑堂トンネルというトンネルがあるのですが、トンネルを出た後の下り区間にちょっと景色のいいポイントがあるのでオススメです。

蓑堂トンネルを出た先で林道のようなダムに向かう道に入っていきます。少々狭いですが、基本的にほかの交通と出会わないので比較的落ち着いて走れます。
平均勾配7%弱の坂を4.5km程度登ると豊丘ダムに到着します。


堤高が80m近くある重力式コンクリートダムなので、堤体は結構迫力があります。

ダム湖は昇竜湖という名前で、これは公募によって決まったものだそうです。字面に格ゲー感がありますが、須坂市には臥竜山・臥竜公園という名所があるので、”竜”というキーワードは親しみのあるものなのかもしれません。

ダムサイトには結構様々な施設があるようです。徒歩だと色々と見てまわりやすそうです。

昇竜湖を一周する道路もあるようなのですが、道路周辺の法面が崩落しているとのことで通行止めでした。堤体の上も含めてぐるっと一周できるとまた面白いと思います。
行き止まりなのでどうしても同じルートを行って帰ることにはなってしまいますが、市街地から10km程度で700m近い標高差があり、気軽な登りルートとして結構重宝しそうな感じです。