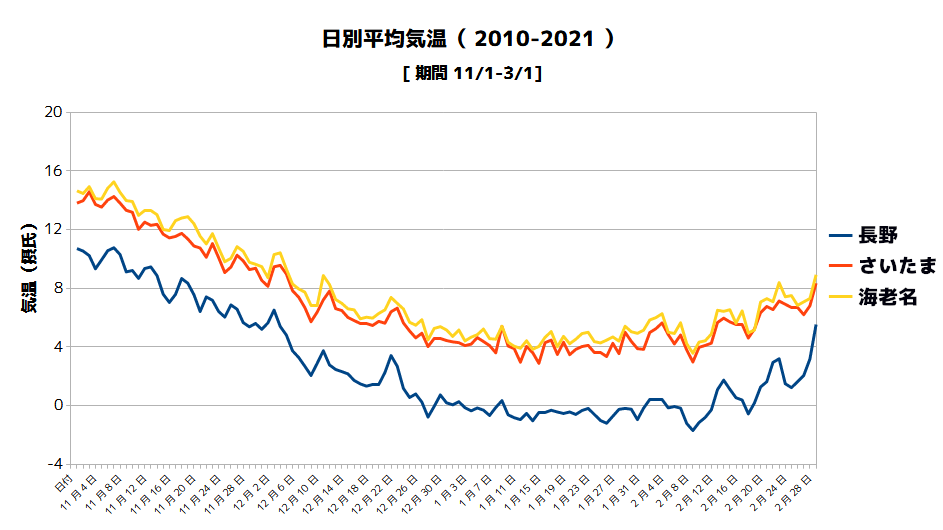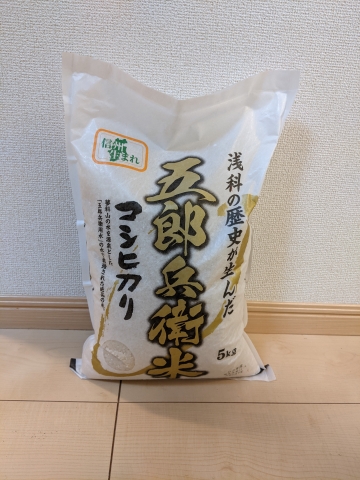しばらく長野県で暮らす中で、長野県固有(?)の年末年始の風習として、以下の2つがあることが分かっているところです。
- 大晦日と元旦にそれぞれ神社やお寺にお参りする”2年参り”
- 大晦日の晩に食べる”年取り魚”
最近何となくこれも長野特有なのではないかと思っていることに、おせち料理を食べ始めるタイミングがあります。
一般的には元旦の朝または昼あたりからおせち料理が食卓に上る場合が多いと思うのですが、長野県においては大晦日の晩からおせち料理を食べ始めることが結構多いようです。
上に挙げた2点との共通点として、元旦よりは大晦日が重視されている傾向が挙げられそうです。”なぜ長野県は大晦日重視なのか”という部分は引き続き謎として残りますが、何か由来のありそうな特徴だと思います。