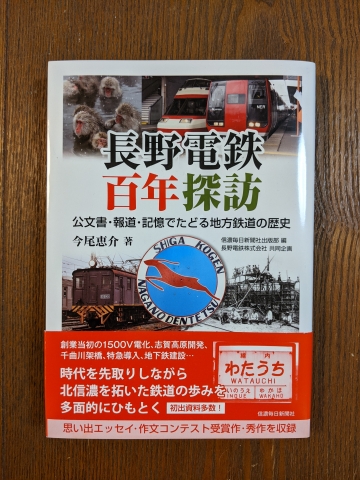松代周辺の千曲川沿いには、一面につる性の植物が植わった畑が広がっています。特徴的な見た目のこの植物は、長いもなんだそうです。

農林水産省の作物統計調査(2019年)によれば、長いもは全国合計の出荷量が128,400tあり、全体の9割程度にあたる113,900tは北海道(63,200t)と青森県(50,700t)が占めています。これに次ぐ全国3位の出荷量なのが長野県(5,010t)となっています。上位2道県が規格外ですが、長野県も一大産地と言って良いのではないかと思います。
長いもは水はけの良い土地でよく育つとのことなので、千曲川による堆積物が中心と思われる松代周辺の土壌は栽培好適地なのかもしれません。
長野市周辺では秋になると地場野菜として長いもが多数出回るので、流通が始まったら入手してみたいと思います。