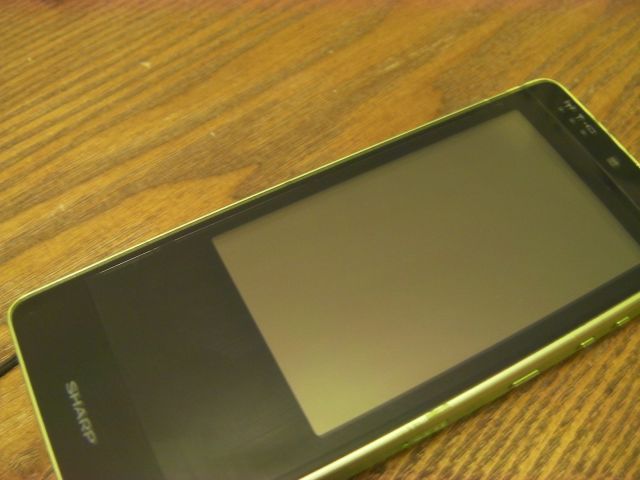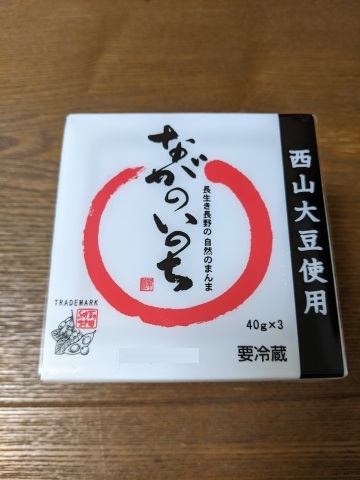2020/10/29以来の久々のファームウェアアップデートがありました。
UIの改善
大きいトピックとしてはまずUIの改善が挙げられています。具体的にどこが改善したのかは検証し切れていませんが、v1.2.16で気がついた動画撮影モードの”ベーシック”と”プロ”が逆になっている問題は修正されたようです。”ベーシック”は”基礎”に名前が変更されています。
液晶画面のタッチによるカメラのウェイクアップ
Insta360 ONE Rは電源ON時に一定時間無操作状態が継続するか、電源ボタンを短く押すと液晶がオフになり、スリープ(?)モードになります。
従来この状態からウェイクアップをする時には再度電源ボタンを短く押す必要があったのですが、Insta360 ONE Rの電源ボタンは誤操作防止のためか結構硬いので、思ったように操作できない場合がありました。
うまく操作できないうちに長押しになってしまい電源がOFFになるなどのトラブルもあったのですが、今回のアップデートで液晶画面を触るだけでウェイクアップするようになりました。これは使い勝手の面では大きな改善だと思います。
まだ自転車で屋外を走るのはちょっと厳しいコンディションなので新ファームウェアを試せませんが、早いところ実戦投入してみたいものです。