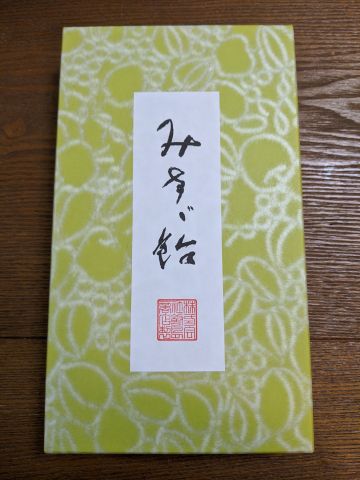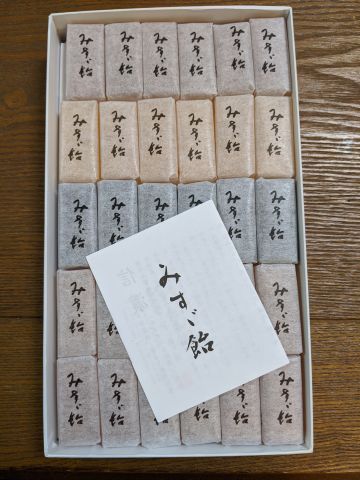ER-4XRのイヤーチップですが、俗に3段キノコと呼ばれる3段フランジイヤーチップを長らく使っています。
一方で、ER-4シリーズにはスポンジ状のフォームイヤーチップも用意されており、遮音性についてはフォームの方に軍配が上がるように思えます。
しかしながら、ER-4用のフォームイヤーチップは少々硬質でガサガサした触感になっており、どうもしっくりこないと感じていました。
イヤホン用のアクセサリを見ていたらER-4に互換性があるというサードパーティ製のイヤーチップを見つけたので、ここしばらくはそちらを使っています。
Crystalline Audio クリスタルチップス
 パッケージです。
パッケージです。
Crystalline Audioというブランドのクリスタルチップスというイヤーチップです。イヤホンに取り付ける筒(コア)の周辺にフォームが巻き付けてある、ER-4用のフォームイヤーチップと同一の構造です。
コアのサイズはS・M・Lの3種類で、ER-4シリーズであればSが互換性のあるサイズとなります。メーカーサイトで各社イヤホンとの互換性を調べることができます。
本体部分のサイズも同様にS・M・Lの3種類です。
 取り出すとこんな感じです。サイズはコアサイズがS、本体サイズはMとなっています。
取り出すとこんな感じです。サイズはコアサイズがS、本体サイズはMとなっています。
使用感
 取り付け状況です。見た目のマッチングも悪くありません。
取り付け状況です。見た目のマッチングも悪くありません。
フォームがER-4純正の物より柔らかく、フィット感が良好に感じます。フォーム特有の遮音性も優秀だと思います。これはフォームのキメが細かいのも一因かもしれません。
また、フォームの表面に薄いコーティングのような加工がされており、これにより装着した時の感触が良いです。耳の穴にガサガサ感がないので快適に装着できます。
フォームは高反発な印象で、冬場でも比較的柔らかな状態を維持しています。一方、柔らかで高反発な分、指でこねた後に復元するスピードが速いので、装着は素早く行う必要があります。
コスト・耐久性
耐久性についてはおよそ1年弱で表面のコーティングが劣化し、ボロボロと崩れてきてしまいました。半年くらいで交代させてあげるとフレッシュな状態を維持できるのではないかと思います。
コスト面は単品で買うと1ペア800円弱、3ペアまとめて買うと700円ほどといったところです。純正の3段キノコと比べると2倍程度のコストになります。
まとめ
少々割高感のある製品ではありますが、性能面を考えると妥当な感じがします。カナル型である以上フォームイヤーチップにしたいという方、どうも純正のイヤーチップが合わないなという方にはオススメできる選択肢です。