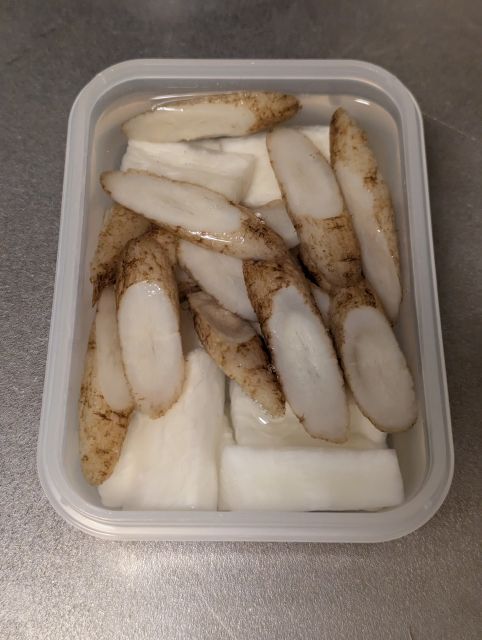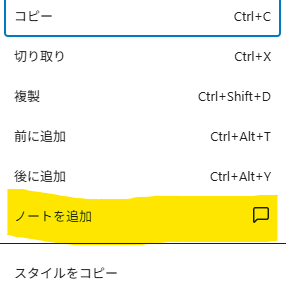すでに長野県は雪の降る日も出てきていますが、この週末は日中は気温が高いという話だったので今シーズン最終となる自転車ツーリングに出かけました。
アメダスの気温を見ると氷点下は脱していそうな感じではあったのですが、自宅近辺でも日陰のエリアは凍っている様子で、心配になったのでほぼ走らずに行程を打ち切って帰ってきました。
雪の後も晴れた日があったものの、やはり日中の気温がそこまで高いわけでもないので日陰を中心に路面にはある程度水分が残ってしまっているようです。
もちろん昼前くらいまで待てば多少は走行できたのかもしれませんが、その時間帯になると車も増えてきますし、そんなに納得いくルートも組めそうにないのでおとなしくあきらめた次第です。
これまでの経験から気象庁の長野アメダスの結果を参考に、1日の平均気温が2度を連続して下回るようだとそろそろ走れなくなるという何となくの目安を作っていますが、2025年は12/6時点で3日連続2度未満なので、やはりこの基準はまあまあ参考にできそうです。
今シーズンは腰痛の問題もあったので、冬の間に乗るときのフォーム見直しなどにも取り組んでみたいと思っています。