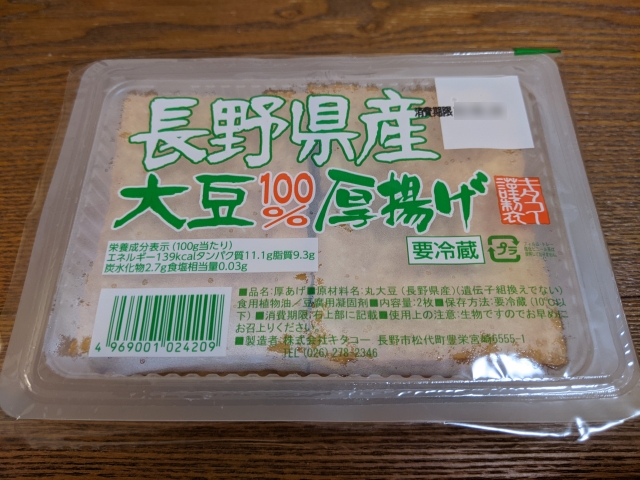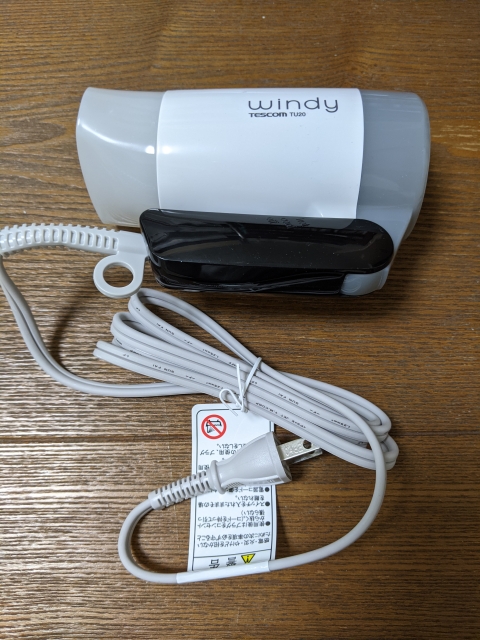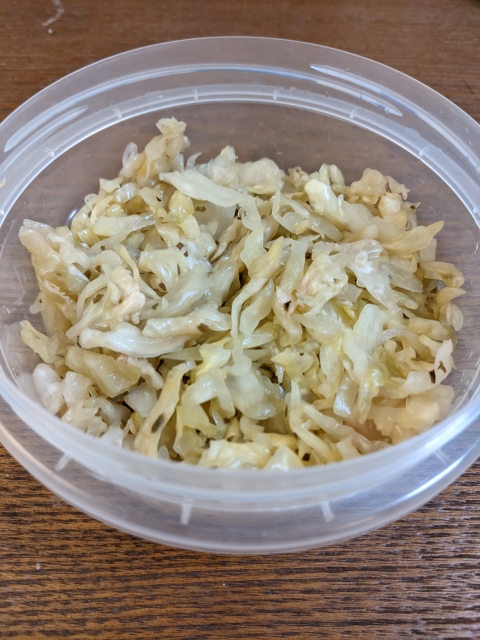Pixel 3a XLのイヤホンジャックにプラグを差し込んだ状態で、プラグに触ったりプラグが動いたりした時にいわゆるガリノイズが発生するように感じたので、イヤホンジャックを清掃してみることにしました。
イヤホンジャックの清掃には歯間ブラシや綿棒がよく使われるそうです。今回は家にあった綿棒の綿部分をむしって、イヤホンジャックに入る程度の径にして使いました。

接点のトラブルなので接点復活剤などの利用も考えられますが、スマートフォンに接点復活剤はあまり使いたくありませんでした。そこでシリコングリス除去用の無水アルコールを含ませてクリーナーとしました。
清掃してみたところ大きなものではありませんでしたがホコリのかたまりが出てきて、清掃後かなりガリノイズは出にくくなりました。
スマートフォンは日々色々な場面で運用されているので、たまにはこうやってイヤホンジャックも清掃した方が良さそうに思いました。