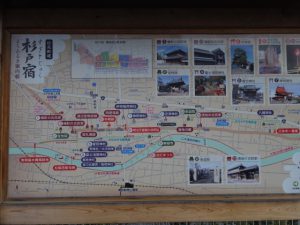ルート100の調査で北川辺に行きましたが、さすがに埼玉大橋の通過リスクが高すぎるように思えたので代替案を検討しました。
利根川に架かる橋(埼玉県内)
- 埼玉県内に架かる自転車が通行できそうな利根川の橋は以下の通りです。
- 坂東大橋(国道462号・本庄市-群馬県伊勢崎市・両側歩道あり)
- 上武大橋(県道14号・深谷市-群馬県伊勢崎市・自歩道専用橋あり)
- 新上武大橋(国道17号BP上武道路・深谷市-群馬県太田市・下流側歩道あり)
- 刀水橋(国道407号・熊谷市-群馬県太田市・自歩道専用橋あり)
- 赤岩の渡し(県道83号・熊谷市-群馬県千代田町・県道扱いの無料渡し船・自転車可(ロードバイクは不明))
- 利根大堰天端(県道20号・行田市-群馬県千代田町・上流側歩道あるが狭あい)
- 昭和橋(国道122号・羽生市-群馬県明和町・両側歩道あり)
- 埼玉大橋(県道46号・加須市-加須市・両側歩道あるが狭あい)
- 利根川橋(国道4号・久喜市-茨城県古河市・両側歩道あり)
橋は色々あるのですが、北川辺周辺となると昭和橋・埼玉大橋・利根川橋の三択となります。昭和橋を選択すると羽生のあたりまでかなり遠回りをしないといけないので、利根川橋で安全に通行できないかを考えてみました。
利根川橋
利根川橋は国道4号の橋りょうで、上下線が別の橋になっています。上下線ともに物理的に区画された歩道があって安全ですが、この歩道の柵には全く切れ目がないので、橋のかなり手前から歩道走行に切り替えておく必要があります。利根川サイクリングロードから進入すると簡単だと思います。
埼玉大橋に比べると安全さは段違いです。
新三国橋へ
利根川橋で利根川を渡った場合、北川辺に行くには渡良瀬川を渡る必要があります。幸い、新三国橋が安全に渡れそうなので新三国橋へ向かいます。利根川橋を渡ってすぐ左折するとほぼ一本道で到着となります。
途中の道は特に標識は出ていませんが、物理的に区画された自転車専用と思われる通行エリアがあります。路面が細かく波打っているので結構体に堪えますが、安全なのは確実です。
道交法上の自転車道ではなさそうですが、歩道と分離された通行エリアがあります。
新三国橋
新三国橋は上流側にのみ歩道があるので、事前に歩道通行に切り替えておきます。片側にしか歩道がないのは不便ですが、こちらも余裕を持って通行可能です。
渡るとちょうど新古河駅付近なので、渡良瀬川の堤防沿いのルートにそのまま入れます。
多少遠回りにはなりますが、こちらの方がよほど安定感はあるルート選択なので、今後北川辺を訪問する際は利根川橋経由のルートをメインに考えてみたいと思います。