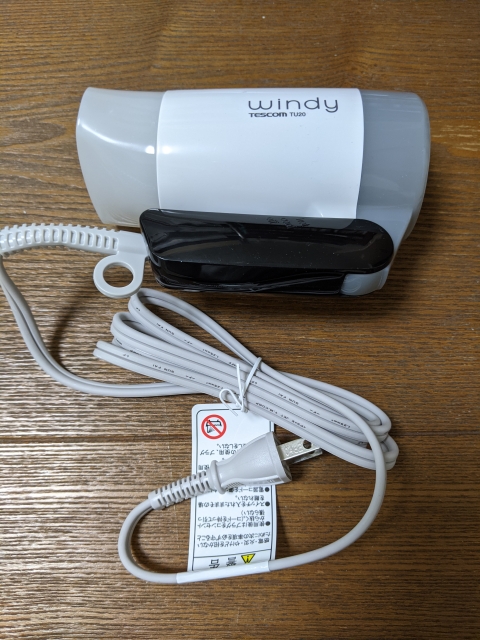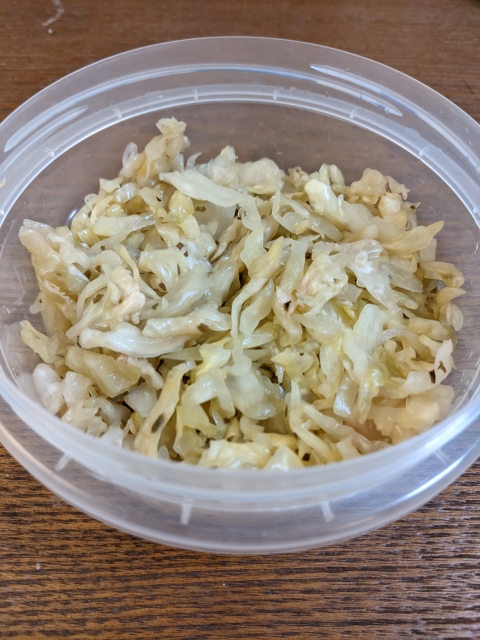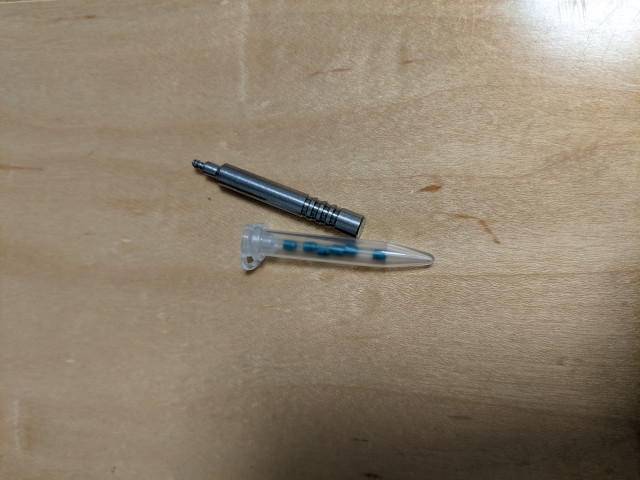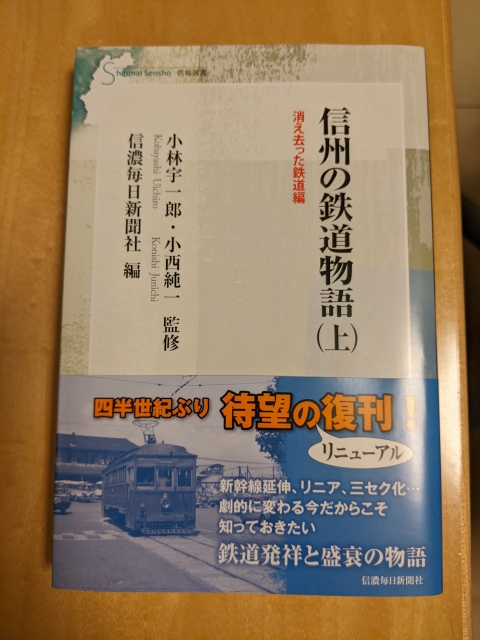最近動画のBGMを時々作っていることもあって、改めてFL Studioの使い方を見直しています。開発元のImage-LineがYoutubeにたくさん動画を公開してくれているので、動画で操作方法やtipsを見るのが分かりやすいです。
見た中でも特に参考になったのが標題のMixing Basicsシリーズです。その名の通りミキシングの手順をテーマごとに解説してくれている動画シリーズです。
例えば下にリンクしてあるのが”Levels”の回なのですが、
- デジタルオーディオにおける”音量”
- クリッピングとは
- ラウドネスとは
等々、気になっているものの良く分からなかった事柄が章立てで解説されています。
特に参考になったのは12:33からの”ノイズを利用したミキシング”です。
人間の聴覚特性上高音域は小さいボリュームでも認識しやすく、低音域はより大きいボリュームが必要なのだそうです。これを利用して低音域から高音域に向けて-4.5dbの音量差があるブラウンノイズをミキシング対象の曲と同時に再生し、各パートごとにパートの音がノイズに混じって認識できる程度に音量を調整するという手法です。
ノイズ越しにギリギリ認識できる程度に各パートを調整することで、結果として全周波数帯にわたって聞きやすい音量バランスになるというものです。実際に使うノイズデータへのリンクも載っていて非常に親切です。
英語なので少々ハードルは高いですが、Youtubeの英語字幕を日本語に自動翻訳すれば大意はつかめるので、明らかに機械翻訳的な違和感のあるところだけ英語字幕に戻して人力で翻訳すれば、思いのほかスムーズに内容を理解できると思います。