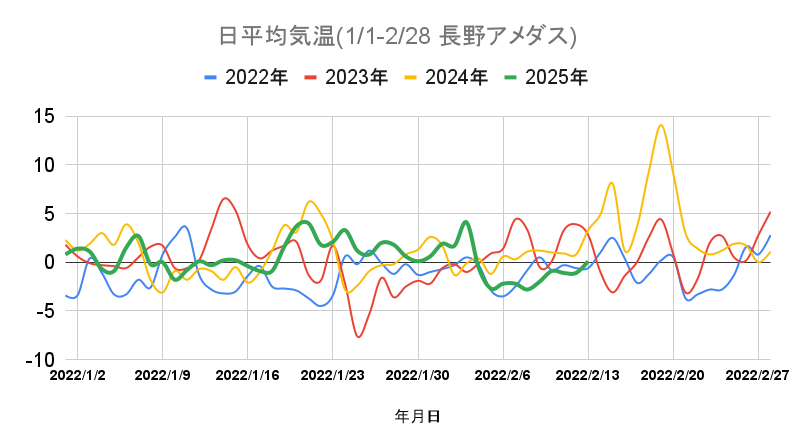期間限定のトクだ値(Suica乗車割引)が設定される一方で、週末パスなどのおトクなきっぷが終売になってしまうそうです。
新幹線eチケットや在来線特急が5月に半額。はやぶさ/はやて/こまち/ひたち/踊り子/スペーシア日光ほか
[トラベルWatch]
週末パス
週末パスはその名の通り任意の土日に利用できるフリーパス型のきっぷです。乗り降り自由のエリアが非常に広く、関東全域から南東北までが乗り降り自由になります。また、別途特急券を購入すると特急や新幹線にも乗ることができます。
地方私鉄の多くの路線が乗り降り自由になるのも良いポイントでした。
以前このきっぷを使った旅行をエントリに書きました。
週末パスを使った鉄道旅行
乗り降り自由の範囲が広くて旅程のアレンジが楽しい切符でしたが、この2025年6月末をもって発売されなくなるそうです。
首都圏週末フリー乗車券
こちらは首都圏では販売されていないのでちょっとマイナーなきっぷかもしれません。東北新幹線、または北陸新幹線の駅から首都圏フリーエリアまでの往復乗車券と、首都圏フリーエリアの乗り降り自由乗車券がセットになっているというものです。新幹線に乗って首都圏に向かい、週末首都圏で用事を済ますときに便利な設定になっています。
価格は長野発の場合は大人6,600円となっており、首都圏フリーエリアの北端である大宮まで往復するだけでも元が取れます。(長野-大宮間は6,820円)
ほとんどの場合首都圏で多少の乗り降りをするので、目的地や乗り降り回数によっては結構おトクになるというきっぷです。
難点としては特急券はセットになっていないので、別途購入する必要があることです。また、有効開始日前日までに購入する必要もあるため、急きょ関東に行く場合などに使いにくいという弱点もあります。
長野に来てからしばらくはよくお世話になりましたが、上記のデメリットもあり最近はもっぱらSuicaで乗車するようになりました。
こういった特殊なルールのきっぷがなくなってしまうのは少々寂しい気もしますが、JR東日本としてはSuica乗車にインセンティブをつけてSuica乗車を促したいという意図があるのも理解できるので、やむを得ないかなという感じもします。