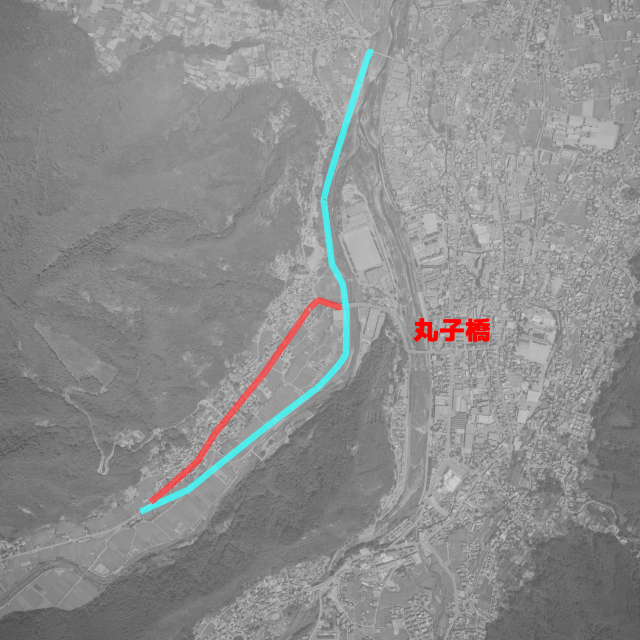時々試してみている炊飯器を使った料理です。以前鶏胸肉を使って蒸し鶏を作りましたが、今回は部位を変えて鶏もも肉で作ってみました。
炊き上がった状況が下の写真です。周辺に細かい鶏肉がたくさんありますが、これは調理時に鶏肉の厚さを均一にするために本体から外した部分です。細かく刻んで炊き込みご飯風のような感じでご飯の方に混ぜ込んでしまいました。

さすがに脂肪分が多めのもも肉だけあって、調理後はぷるぷるした柔らかめの仕上がりになりました。脂が抜けるせいなのか肉自体が結構しぼんでしまうので、ちょっと大きめの鶏肉を使うとちょうど良くなりそうです。

下味は塩コショウで軽くつけただけなのでこの後お好みのたれでいただきます。面倒であれば市販の焼き肉のたれ的なものでもおいしいです。