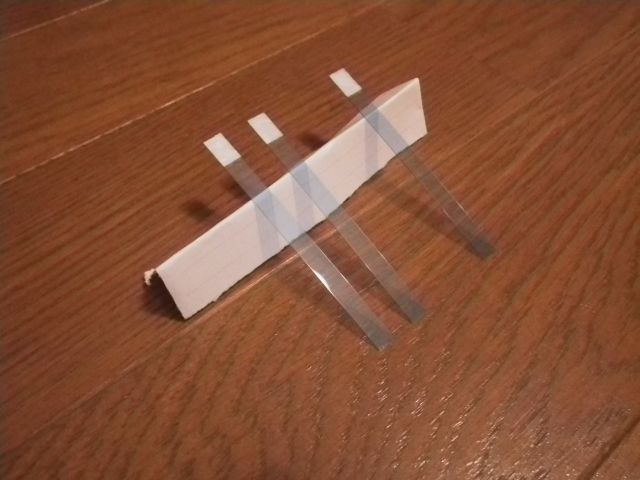ミドルハイレンジを埋めるべくGCNを小改良したのがR9 285のTongaコアだと思っていたのですが、どうもそうではないようです。
後藤弘茂のWeekly海外ニュース AMD、新GPU「Tonga」がHSAの最終形であることを明らかに
[PC Watch]
TongaコアはHSAにおけるGPUアーキテクチャの最終形で、これをAPUに実装することでHSAアーキテクチャも最終形に到達するそうです。
現状のGPUではコンテキストスイッチ(プロセス切り替え時にCPUの状態を切り替えること)を簡単に行うことができないそうです。
これはGPUが元々グラフィックス処理を前提に設計されているためで、フレームを描画し終えるとコンテキストも消去してしまっていたため、切り替えを考える必要はなかったからのようです。
ところが、HSAではGPUにもCPU的な動きをしてもらう必要がある、ということでTongaコアではマルチコアCPUのように柔軟なコンテキストスイッチが可能になっているとのことです。
というわけでちょっとテクニカルな内容ということもあってあまり話題に上がらなかったのかもしれませんが、後から登場したR9 285は結構重要なマイルストーン的製品と言えそうです。
R9 285のTongaコアは一部の機能が無効化されているという情報もあるので、今後は完全版Tongaコア採用製品やAPUにTongaコアを搭載した製品が登場してくるのではないかと期待できます。