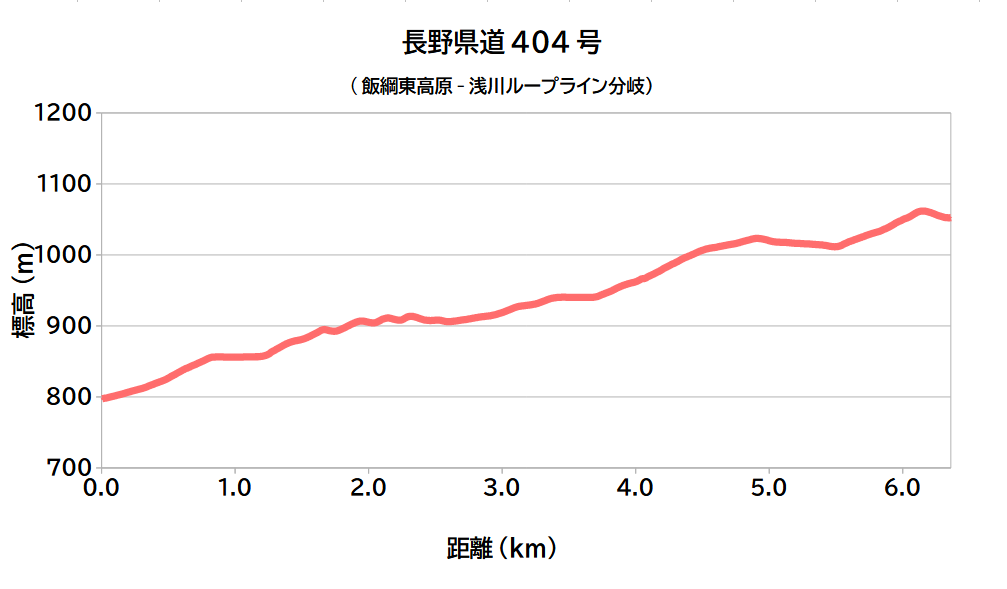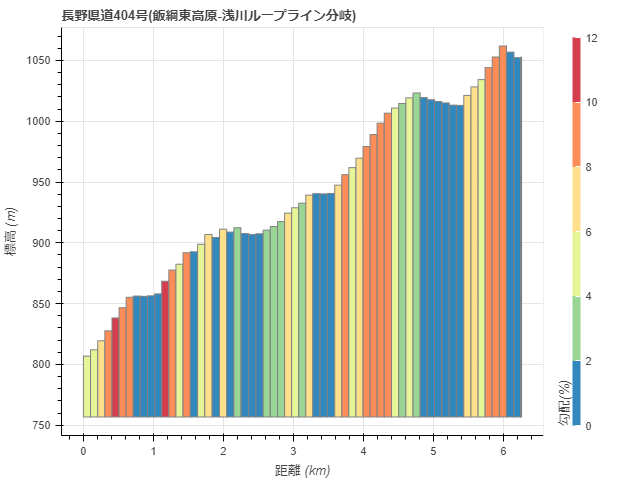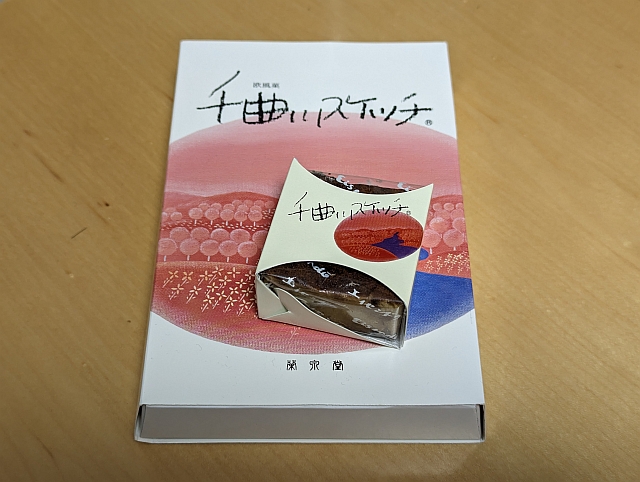バージョン23.7.2がリリースになりました。
AMD Software: Adrenalin Edition 23.7.2 Release Notes
[amd.com]
今回は新たにゲームタイトルをサポートしているわけではなく、純粋にバグフィックスをメインとしたメンテナンスリリースのようです。
COD:MW IIなど個別のゲームタイトルに関するバグフィックスも含まれています。
いくつかある修正点の中で気になったのは、「Adaptive-sync有効時に画面がブラックアウトする場合がある」というものです。問題が発生する製品の例としてRX7900XTが挙げられていますが、この現象はRX7600を使っている我が家でも発生することがあります。今回のバージョンアップで修正されるのであればとても助かります。
ドライバのリリースペースが元に戻りつつある感じがあるので、引き続きRX7600への最適化があるのか楽しみに待ちたいと思います。